医院からのお知らせ
information
【歯科医監修】親知らず抜歯の流れと費用の目安を徹底解説!
25.11.05
カテゴリ:医院からのお知らせ
【親知らず抜歯の必要性とその判断基準】
◇親知らずを抜いた方が良いケース
親知らずを抜いたほうが良いかどうかは、歯科医師が口腔内の状態や将来的なリスクを総合的に判断して決めます。一般的に以下のようなケースでは、抜歯を推奨されることがあります。
①智歯周囲炎(親知らず周囲の炎症)が起こる場合
親知らずの周りの歯肉が赤く腫れたり、痛みや排膿があったり、細菌が溜まりやすく、慢性的に炎症が起きている状態です。
→放置すると歯周病や隣の歯への感染リスクが高まります。
②親知らずが横向きや斜めに生えている場合
顎の骨に埋まっていたり、半分だけ歯肉から出ている(埋伏歯)と、手前の歯を押して、他の歯が痛かったり、腫れる原因になります。
→この状態では噛み合わせに影響したり、腫れや痛みの原因になりやすいです。
③虫歯や大きな炎症を起こしている場合
歯ブラシが届きにくく、虫歯や細菌感染リスクが高くなります。親知らずの虫歯が隣の歯に広がる可能性があります。
→治療が困難な場合は抜歯が最適な選択になります。
④顎や周囲組織に影響が出る場合
親知らずの周囲の骨や神経に炎症や腫れが起きたり、顎関節に負担がかかり痛みや腫れが頻発することがあります。
→骨の健康を保つために早めに受診しましょう。
⑤将来的に問題が起こる可能性が高い場合
歯並びを乱す可能性があったり、親知らずの位置や生え方が将来的に腫れや痛みを引き起こす可能性があります。
→特に若い時期に抜歯をすると回復も早くリスクが少ないとされています。

◇親知らずを抜かなくても良いケース
親知らずは必ずしも抜かないといけないわけではなく、条件が整っていればそのまま残して問題ないケースもあります。
①まっすぐ正常に生えていて、噛み合わせに参加している状態
親知らずが上下とも正しい位置にまっすぐ生えていて、しっかりと噛み合わせに関与している場合は抜く必要はありません。
噛む機能を補ってくれたり、将来的にブリッジなどの支えの歯として使えることがあります。特に痛みや腫れがない場合は『健康な歯』として維持可能です。
→定期的な歯科衛生士による清掃と定期検診を行っていれば問題ありません。
②歯肉や周囲に炎症や痛みがない場合
親知らずの周囲が健康で炎症などがない状態であれば抜歯は必要ありません。毎日のブラッシングが行き届く状態で歯や歯肉が清潔に保たれており、腫れや出血などの兆候がなければ経過観察で十分です。
③清掃がしやすい位置に生えている場合
親知らずの最大の問題点は『磨きにくさ』です。しかし、歯ブラシやデンタルフロスが届く位置に生えている場合は、虫歯や炎症のリスクも低く、保存が可能です。
④隣の歯(第二大臼歯)に悪影響を与えていない場合
親知らずが隣の歯を押したり、虫歯を広げたりしていない場合も抜歯の必要はありません。特にレントゲンで歯根や歯槽骨に異常が見られなければ経過観察で十分な場合が多いです。
⑤完全に骨に埋まっており、問題を起こしていない場合
『埋伏智歯(全く生えていない親知らず)』の中には完全に骨の中に埋まっていて炎症や痛みを引き起こさないケースがあります。この場合は位置によっては無理に抜くと神経損傷などのリスクがあるため、抜歯せずに定期的なレントゲンやCTでの経過観察が必要です。
⑥高齢で症状がなく、抜歯リスクが高い場合
年齢が上がると親知らずの根が骨と強く癒着していることがあり、抜歯による神経損傷や出血、感染リスクが高まることがあります。そのため、症状がない限り無理には抜かず、経過観察と清掃指導で対応します。

【親知らずを放置するとどうなるか】
親知らずは生え方や位置によってトラブルを引き起こしやすく、放置すると口腔内だけでなく全身にも影響を及ぼす可能性があります。ここでは親知らずを放置した場合に起こりやすい代表的なリスクと症状を解説します。
①智歯周囲炎を起こす
親知らずの周囲の歯肉に細菌感染が起きて腫れる症状のことを言います。生えかけや半分埋まった親知らずは歯肉の隙間に汚れや細菌が入り込みやすく、炎症を繰り返すことがあります。
・歯肉の腫れ、痛み
・口が開けにくい
・頬の腫れや発熱
・飲み込み時の痛み
放置すると顎やリンパ節まで炎症が広がることもあり、抗菌薬や抜歯治療が必要になることも。
②虫歯や歯周病のリスクが高まる
親知らずは位置的に歯ブラシが届きにくく清掃が不十分になりやすいため、細菌が繁殖しやすい環境です。
・親知らず自体の虫歯
・隣の歯(第二大臼歯)の虫歯
・歯周病の進行
これらのリスクが高まってしまいます。ケアが行いにくい状態であれば注意が必要です。
③顎や頬の痛み、腫れ
炎症が進行すると、顎の骨や周囲の軟組織にまで炎症がおよび、頬が大きく腫れたり、顎の痛みで口が開かないことがあります。炎症が強い場合は切開処置が必要なことがあります。
④噛み合わせは歯並びへの影響
親知らずが斜めや横向きに生えている場合、隣の歯を押してしまい、前歯の歯並びが乱れることがあります。特に矯正治療後に放置するとせっかく整えた歯並びが再びずれてしまうリスクも。
⑤骨や神経への悪影響
埋まったままの親知らずが長期間放置されると歯の周囲に嚢胞と呼ばれる袋状の病変ができることがあります。嚢胞が大きくなると次のような重度なトラブルを引き起こすことも…。
・顎の骨が溶ける。
・神経を圧迫して痺れが出る。
・骨や隣の歯を侵す。
⑥全身への炎症拡大
重度の感染を放置すると、細菌が血流を通じて全身に回ることがあります。稀に命に関わる感染症を引き起こすこともあるため、腫れや痛みを繰り返す場合は早めの歯科受診が重要です。

【親知らず抜歯の手術と流れ】
◇抜歯前の準備
親知らずを安全に抜歯するためには事前の診査、準備が欠かせません。
①レントゲン、CT撮影
歯の生え方や、骨や神経との位置関係を正確に把握するために撮影を行います。特に下の親知らずは、下歯槽神経が近いことが多いためCT撮影で立体的に確認する必要があります。
②口腔内の清掃管理
炎症や感染がある場合は抜歯前に治療を行い、口腔内を清潔な状態に整えます。細菌が多い状態で抜歯を行うと、腫れや炎症のリスクが高まります。
③服薬、持病の確認
抗凝固薬(血をサラサラにする薬)や糖尿病などの持病がある場合は抜歯の方法やタイミングを調整します。必要に応じて医科の主治医と連携を行うこともあります。
④食事と当日の準備
抜歯の2時間前に軽めの食事を済ませましょう。十分な睡眠と体調管理を心がけましょう。

◇抜歯手術の流れ
親知らずの抜歯は生え方によって所要時間が異なりますが、通常は30分〜60分程度で完了します。
①麻酔の実施
局所麻酔を行い、痛みを感じない状態にしてから手術を始めます。必要に応じて、笑気麻酔や静脈内鎮静法を併用する場合もあります。
②歯肉の切開(埋伏歯の場合)
歯が歯肉の下に埋まっている場合はメスで歯肉を切開します。
③骨の削除、分割
歯が大きい、根が曲がっているなどの場合は歯を分割して少しずつ取り出します。骨を削る際も必要最小限の処置で行います。
④抜歯と洗浄
歯を取り除いた後、抜歯窩(穴)を洗浄し、異物や細菌を除去します。
⑤縫合
必要に応じて歯肉を糸で縫います。縫合した後は1週間前後で抜糸を行います。
⑥圧迫止血
ガーゼを噛んで圧迫止血をします。出血が止まったら血餅と呼ばれる『自然のかさぶた』が形成されます。

◇抜歯後の注意点(アフターケア)
・当日は強いうがい、喫煙、飲酒を控えましょう。
・麻酔が切れるまで(大体2〜3時間)は食事を控えましょう。
・腫れや痛みは2〜3日目をピークに1週間ほどで落ち着きます。
・激しい運動や入浴は控えましょう。
・痛みや腫れが長引く場合はドライソケットや感染の可能性があるため早めに再受診しましょう。
※親知らずの抜歯手術は正確な診断と丁寧な準備によって安全に行われます。不安を感じた時は、歯科医師に相談をして事前に手順を理解しておくことが安心への第一歩です。適切なケアと指導のもとで、回復をスムーズに進めましょう。

【親知らず抜歯にかかる費用の目安】
親知らずの抜歯費用は歯の生え方や処置の難易度、保険の適用範囲によって大きく異なります。ここでは一般的な費用の目安とその内訳について説明します。
◇保険診療と自由診療の違い
親知らずの抜歯は、多くの場合、保険が適用される治療です。ただし、処置内容や麻酔方法、設備によって自費となるケースもあります。(以下は3割負担の場合の例です。)
・通常の抜歯(比較的簡単な処置):約1,000〜2,500円
・埋伏智歯(外科的処置、切開あり):約3,000〜5,000円
・難抜歯(CT撮影、分割抜歯など):約5,000〜8,000円
・静脈内鎮静法(自費):約15,000〜30,000円
・抜歯後の投薬、処置(抗生剤、痛み止め):約500〜1,000円
一般的には1本あたり、3,000〜10,000円程度(保険適応)で済むことが多いです。ただし、親知らずが4本生えている場合や大学病院での外科手術になる場合はもう少し高くなることもあります。

◇費用が変動する主な要因
親知らずの位置や向き(埋伏、横向きなど)、神経との距離(CT撮影の有無)、麻酔の種類(局所麻酔/笑気麻酔/静脈内鎮静)歯科医院の設備、診療方針、抜歯後の処置、薬の内容などで変動することがあります。
◇高額になるケースとその理由
顎の骨の深部に埋まっており、外科手術の処置が必要な場合や大学病院や口腔外科での対応が必要な難症例な場合、または笑気麻酔や静脈内鎮静法、CTなど自費のオプションを利用する場合に高額となることがあります。
【親知らず抜歯後の注意点】
親知らずを抜歯した後は傷口の回復を妨げないように正しいケアと生活管理を行うことが大切です。ここでは抜歯後に気をつけたいポイントをわかりやすく解説します。
①抜歯当日は『血を止めること』が最優先
抜歯後すぐは出血が続きやすいため、まずはガーゼを20〜30分しっかり噛んで止血しましょう。うがいや口を強くすすぐ行為は血の塊(血餅)を流してしまうため、当日は避けてください。
・唾を強く吐き出さない。
・ストローを使わない。
・入浴や激しい運動は避ける。

②食事に関する注意点
食事の面でも注意点がいくつかあります。
・抜歯当日:柔らかくて温かすぎない食事(おかゆやスープ)
・翌日以降:傷口を避けてゆっくり噛む
・避ける食べ物:硬い、辛い、熱い、粘着性のあるもの(せんべい、カレー、ガムなど)
※アルコールやタバコは厳禁です。

③入浴、運動、睡眠の注意点
入浴や運動は出血や炎症を悪化させ理ことがあります。以下のことに気をつけましょう。
・当日は入浴や運動は激しい控える。シャワー程度にとどめるのが安心。
・頭を高くして休むことで腫れを軽減。

④歯磨き口腔ケアの注意点
抜歯当日は傷口を避けて優しく磨くようにしましょう。傷の近くは強く当たらないように注意します。処方されたうがい薬や抗生剤は指示通りに使用しましょう。
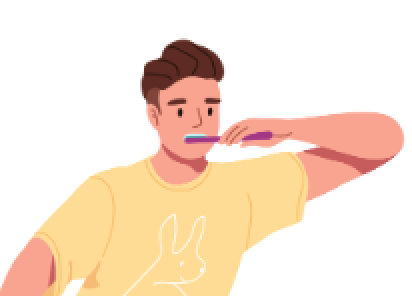
【まとめ】
親知らずの抜歯は生え方や顎の状態によって難易度や費用が異なります。事前の診断と信頼できる歯科医師のもとで治療を受けることで安心して抜歯が行えます。術後は適切なケアを心がけ、早期回復を目指しましょう。

