医院からのお知らせ
information
【歯科医監修】虫歯治療の基本知識と予防法を徹底解説!
25.11.06
カテゴリ:医院からのお知らせ
【虫歯の基礎知識とその進行】
①虫歯とは何か
虫歯とは、虫歯菌(主にミュータンス菌)が食べかすや糖分を分解して酸を作り、その酸が歯を溶かしてしまう病気です。初めは白く濁ったり、小さな穴があく程度ですが、進行すると歯の神経まで到達して、強い痛みや炎症を引き起こします。放置すると歯を失うこともあります。虫歯はそのままにしていても自然に治ることはないため、早期発見と適切な治療が非常に重要となります。

②虫歯の進行段階:一般的にCO〜C4までの5段階に分けられます。
・CO(初期虫歯、脱灰)
歯の表面のエナメル質が酸によって溶け始め、白く濁って見える状態です。痛みはありませんが、放置すると進行していきます。フッ素や正しい歯磨きで再石灰化が可能です。
・C1(エナメル質の虫歯)
エナメル質に小さな穴があいた状態です。痛みは少ないですが、削って穴を埋める処置が必要になります。状態によっては、フッ素塗布による経過観察の場合もあります。
・C2(象牙質まで進行)
虫歯が象牙質まで進行すると、冷たいものや甘いものがしみるようになります。削って、詰め物や被せ物で治療します。
・C3(神経まで進行)
虫歯が神経まで進行すると、ズキズキと強い痛みが出ます。根管治療(神経の治療)が必要になります。
・C4(歯根だけ残った状態)
歯の大部分が崩壊し、神経が死んだ状態になると、一時的に痛みは和らぎます。腫れや膿がたまることもあり、抜歯が必要になるケースが多くなります。

早期に治療を行うことで、痛みや費用の負担を軽減することができます。
【虫歯の治療法】
虫歯の進行段階ごとの代表的な治療法をわかりやすくまとめていきます。
①CO:歯の表面が白く濁る、茶色に変色する。症状はない。
・削らずに『フッ素塗布』や『シーラント』などの予防処置を中心に行う。
・正しいブラッシングや食生活の改善で再石灰化を期待する。
②C1:エナメル質に小さな穴があいている状態。痛みはほとんど感じない。
・虫歯の部分を削り、詰める処置を行う。
・フッ素塗布による進行抑制の処置で削らずに経過観察することもある。
③C2:虫歯が象牙質まで進行。冷たいものや甘いもので痛みが出る。
・虫歯の部分を削り、レジンやインレーで詰め物の処置を行う。
・症状によっては治療に痛みを感じる場合がある。その場合は局所麻酔を行う。
④C3:虫歯が神経まで達した状態。ズキズキと強い痛みが出る。
・根管治療を行い、感染した神経を取り除き、消毒を行い、根管充填。
・その後、被せ物を入れる。
⑤C4:歯の大部分が崩壊し、歯根だけ残った状態。
・多くは抜歯が必要となる。
・その後、ブリッジや入れ歯、インプラントの治療になる。
虫歯は、早期であれば削らずに治せることもありますが、進行すると神経を取ったり抜歯をするなど大がかりな処置が必要となります。定期的な検診と早めの受診が、歯を長く健康に保つために大切です。
【虫歯治療の流れと注意点】
むし歯治療は進行度に応じて内容や治療内容が異なりますが、基本的な流れは共通しています。一般的な虫歯治療の流れと、治療を受ける際に知っておきたい注意点をわかりやすくまとめます。
◇虫歯治療の流れ
①診察、検査:歯科医師が口腔内の状態を確認する。
・目視や探針による虫歯チェック
・レントゲン撮影での歯の内部や隣接面の状態をチェック
・痛みの原因や進行度を正確に診断
②治療計画の説明:虫歯の状態や治療内容、費用、通院回数などの説明を受ける。
・『削って詰める』『根管治療を行う』『抜歯をする』など治療方針を決定
・保険診療と自由診療に関してもこの時点でカウンセリングを受けましょう
※納得してから治療に進むことが重要になります!!
③虫歯の除去(削る処置):虫歯の部分を削り、感染した組織を取り除く。
・初期であれば最小限の処置で済む
・中程度〜重度の場合は局所麻酔を使用して痛みを軽減させて処置を行う
※近年は削りすぎを防ぐため、最小侵襲治療が主流です。
④詰め物、被せ物の装着:削った部分を補うために行う。
・小さな虫歯であれば、レジンで詰める
・大きめの虫歯であれば、インレーやクラウンを入れる
※保険であればレジンや銀歯、自費であればセラミックなどのいい材質の選択が可能です。
⑤根管治療(虫歯が重度の場合):根管内をきれいにして消毒する。
・1本の歯に対して最低でも3〜6回は通院が必要となる。
・根管治療後、補綴治療に入る。
⑥定期検診、メインテナンス:再発防止のために定期的にチェックする。
・3〜6ヶ月ごとの受診がおすすめ
・クリーニングやフッ素塗布も行いましょう

◇虫歯治療の注意点
①痛みがなくても放置しない
・初期段階では痛みがなくても進行している場合があります。放置すると治療も大がかりとなり、さまざまな面で負担が増えてしまいます。
②治療を途中で中断しない
・根管治療や被せ物の治療を途中でやめてしまうと細菌が再び侵入して再発することも。
③治療後のセルフケアを怠らない
・毎日の丁寧なブラッシング(デンタルフロスや歯間ブラシも併用する)
・フッ素配合の歯磨き粉を使用する
・砂糖の摂取や間食の頻度を減らす
④仮蓋、仮歯の取り扱い
・治療途中の仮蓋や仮歯が取れてしまうと再感染のリスクが高まる
【虫歯予防のためにできること】
虫歯は『予防』が何より大切です。一度削った歯は元には戻らないため、日常のケアや生活習慣を見直すことが虫歯予防の基本になります。虫歯を防ぐためにできることを具体的にまとめます。
①正しいブラッシングの習慣化:歯磨きは虫歯予防の基本です!
・1日2〜3回時間をかけて丁寧に行う
・力を入れすぎず、細かく動かして磨く
・フロスや歯間ブラシを使用して、歯と歯の間の汚れを除去する
②フッ素を積極的に取り入れる:フッ素は虫歯予防に欠かせない成分です!
・歯の再石灰化を促進し、強い歯を作る
・フッ素入りの歯磨き粉や洗口液、歯科医院でのフッ素塗布を活用する
・特に子どもや初期虫歯がある場合に効果的
③食習慣の見直し:虫歯菌は糖をエサにして酸を出し、歯を溶かします!
・砂糖の摂取、間食の頻度を減らす
・食事は規則正しく、だらだら食べをしない
・キシリトールを活用して虫歯菌の働きを抑制、唾液の分泌を促進させる
④唾液の力を高める:唾液は虫歯予防には欠かせない『自然のバリア』です!
・よく噛んで唾液の分泌を促進させる
・水分をこまめにとって、ドライマウスを避ける
・ストレスや口呼吸は唾液の分泌を抑えてしまうため注意が必要
⑤定期的な歯科検診を受ける:自分では気づきにくい初期虫歯をプロがチェック!
・3〜6ヶ月に1回の定期検診がおすすめ
・歯科衛生士によるクリーニングでセルフケアでは落とせない歯石やバイオフィルムの除去
・早期発見、早期治療で費用も負担も軽減
⑥生活習慣を整える:虫歯は生活習慣とも深く関係しています!
・睡眠不足やストレスは唾液の分泌を悪くしてしまう
・偏った食事は口腔内環境を悪化させる
・禁煙も重要(口腔内を乾燥させ、血流も悪くする)
虫歯予防は歯を磨くだけでなく、『食事・生活・習慣』全てのバランスが重要です。セルフケアと歯科医院での定期検診を組み合わせることで、、虫歯のリスクを大幅に減らすことができます。小さな心がけの積み重ねが、一生自分の歯で食べるための最大の予防策となるのです。
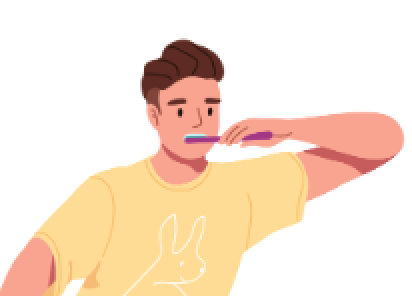
【まとめ】
虫歯は誰でもなり得るとても身近な病気ですが、正しい知識と日常のケアによって十分予防と管理が可能です。もし異変を感じたらはやめに歯科医院を受診し、進行を止めることが大切です。定期的な歯科受診と正しいブラッシング習慣、フッ素の活用、正しい生活習慣で虫歯を防ぎ、大切な自分の歯を守りましょう。


